> 人を知る > 社員紹介
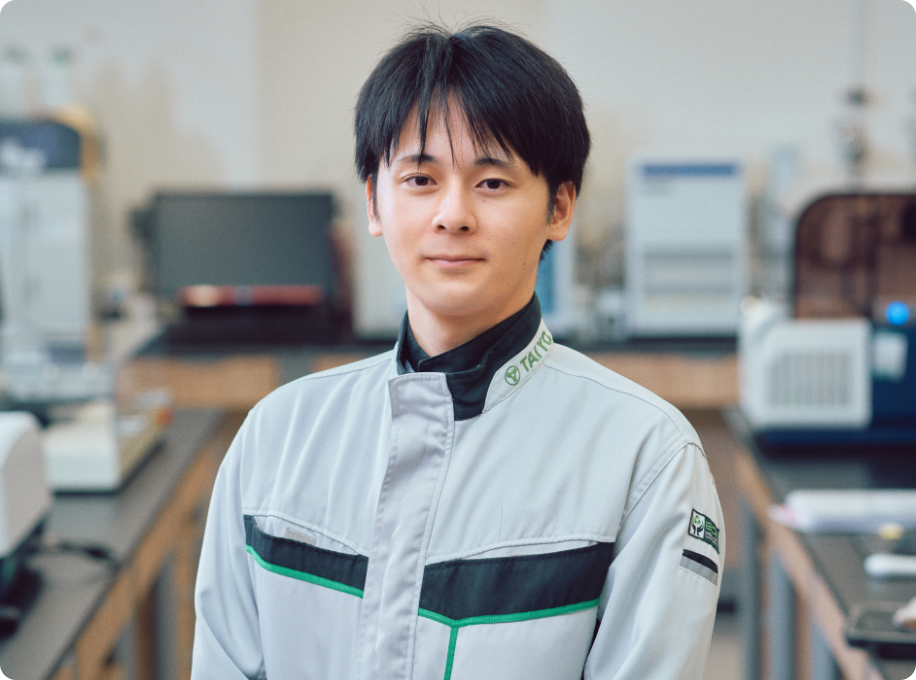
研究
AI技術を活かし、研究開発にDXを
研究本部 研究部 開発推進課
太陽ホールディングス
2020年 新卒入社
H.S.
※ インタビュー内容は取材当時のものです
太陽ホールディングス
研究本部
2020年〜2021年
AI関連技術の知識習得のかたわら、高分子や低分子の合成といった複数のテーマに関わる。
太陽ホールディングス
研究本部
2021年~2022年
エレクトロニクス材料の色調予測に関して、簡易的なアプリケーション化の検討や、ソルダーレジスト製造における各工程課題のデータや化学分析、理論計算の検証などを実施。
太陽ホールディングス
研究本部
2023年〜
当社材料への機械学習適用課題を把握しつつ、理論計算やAI技術に着目し実験と計算両輪のあり方にむけて検討を継続中。

化学で社会にインパクトを与えるための選択肢
就職活動では、大学時代に専攻していた化学のバックグラウンドを活かしたいと考えていました。関心があったのは、基礎化学品よりも高機能品の分野。携わる材料の使用用途が分かり、社会に対する価値提供の手応えを感じながら仕事ができるほうが自分にとってはイメージしやすく、面白そうだと感じたからです。
学会に参加した時、ブースを出展していた太陽ホールディングスに出会いました。そこで担当者の方と話す中で、電子材料分野は今後も成長していくことや、今がまさに事業拡大などの変革期であることを知り、どんどん挑戦していく雰囲気が会社とともに成長していきたい自身の価値観と一致し興味を持つように。選考を受ける過程でも、堅苦しい雰囲気は一切なく、芸術的な観点も積極的に取り入れるなどのユニークな感性と、しっかりとした理論を兼ね備えた面白い会社だと思いました。そのまま内定をもらい、入社を決意しました。
- -08:30
- 出社、メールチェック
- -09:00
- 終夜計算の確認とデータまとめ
- -10:30
- 実験(計算、AI技術のためのデータ採取及び検証)
- -15:00
- 社外打合せ
- -16:00
- コードの改良と終夜計算の準備
- -17:00
- 退社

自ら動き、試行錯誤を楽しむ
事業の成長を支え、未来を創ることをミッションに理論計算やAI技術を用いた事業課題解決の可能性を模索するのが私の仕事。今後AI技術は間違いなく社会全体で発展していく分野なので、会社として強化していかなければ乗り遅れてしまうという危機感もあり、この部署への配属は「挑戦するチャンスだ」と思いました。もともとAI技術などのバックグラウンドはありませんでしたが、コーディングなどの勉強を一からスタート。もちろん取り組み始めた当初は分からないことばかりで大変でしたが、注目されているAI技術などを知っていくことで、どのように会社に活かせるのか考えるのが段々面白くなってきました。
また、社内でさらにAI技術の適用範囲を広げていくため、我々の研究成果をアピールして有効性を認知してもらえるよう努めました。その甲斐もあり、興味を持ってくれた部署から声がけしていただくことも増えました。しかし、いつまでも待っているだけではなく、開発部門との研究結果報告会などから情報収集して、どんな課題がありそうか自ら探索することにも取り組んでいます。AI技術の応用で材料開発を加速させ、さらに組織や事業が成長するために何ができるか考えながら、試行錯誤を楽しんでいます。

化学×DX人材だからこそ提供できる価値
様々なアルゴリズムはアカデミックなどの専門家によって生み出されていますので、私たちはいかにこれを材料開発に活用するかに重きを置いています。社内にIT事業もある中で研究部がAIに取り組む理由は、化学系である私たちでなければ分からない視点があるからです。たとえば、光で硬化させて使用するソルダーレジストについて光の吸収を予測する際、化学構造、電子状態など、どの値に着目すれば良いのか検討する必要があります。また、化学の知識を活かし、実際の研究開発現場に必要とされるツールをつくることが求められます。
全社的にもAI技術は未知の分野。最新技術を勉強できる良い環境にいることに感謝しつつ、これを活かさなければという使命感もあります。得られた知見を自分だけに留めておくのではなく、自身の成長とともに会社や事業の成長、さらには社会の進化につなげていきたいです。そのためにも社内だけでなく、社外の協力会社と連携して実用化を目指しています。提供される実験データや装置の情報に加え、自分達でも手を動かしデータを蓄積し、システム開発の専門家とともに、さらに磨きをかけています。

研究K.S.研究本部 研究部 新素材研究課
太陽ホールディングス株式会社

研究H.S.研究本部 研究部 開発推進課
太陽ホールディングス株式会社

研究J.M.研究本部 企画部 PoC課
太陽ホールディングス株式会社

開発Y.N.基板技術開発部 基板技術課
太陽インキ製造株式会社

開発K.T.絶縁材料開発部 PKG材料開発課
太陽インキ製造株式会社
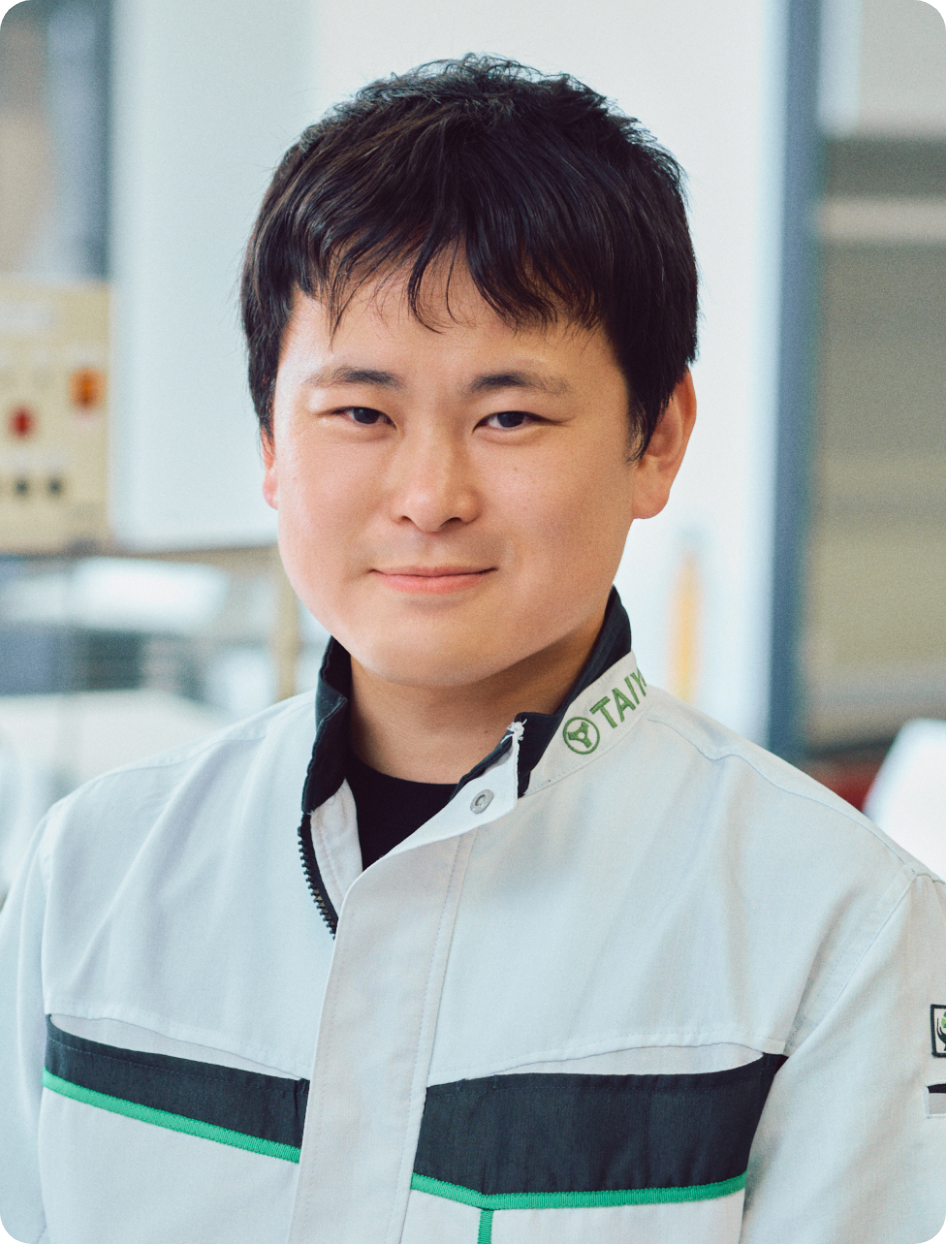
開発T.N.基板技術開発部 基板技術課
太陽インキ製造株式会社
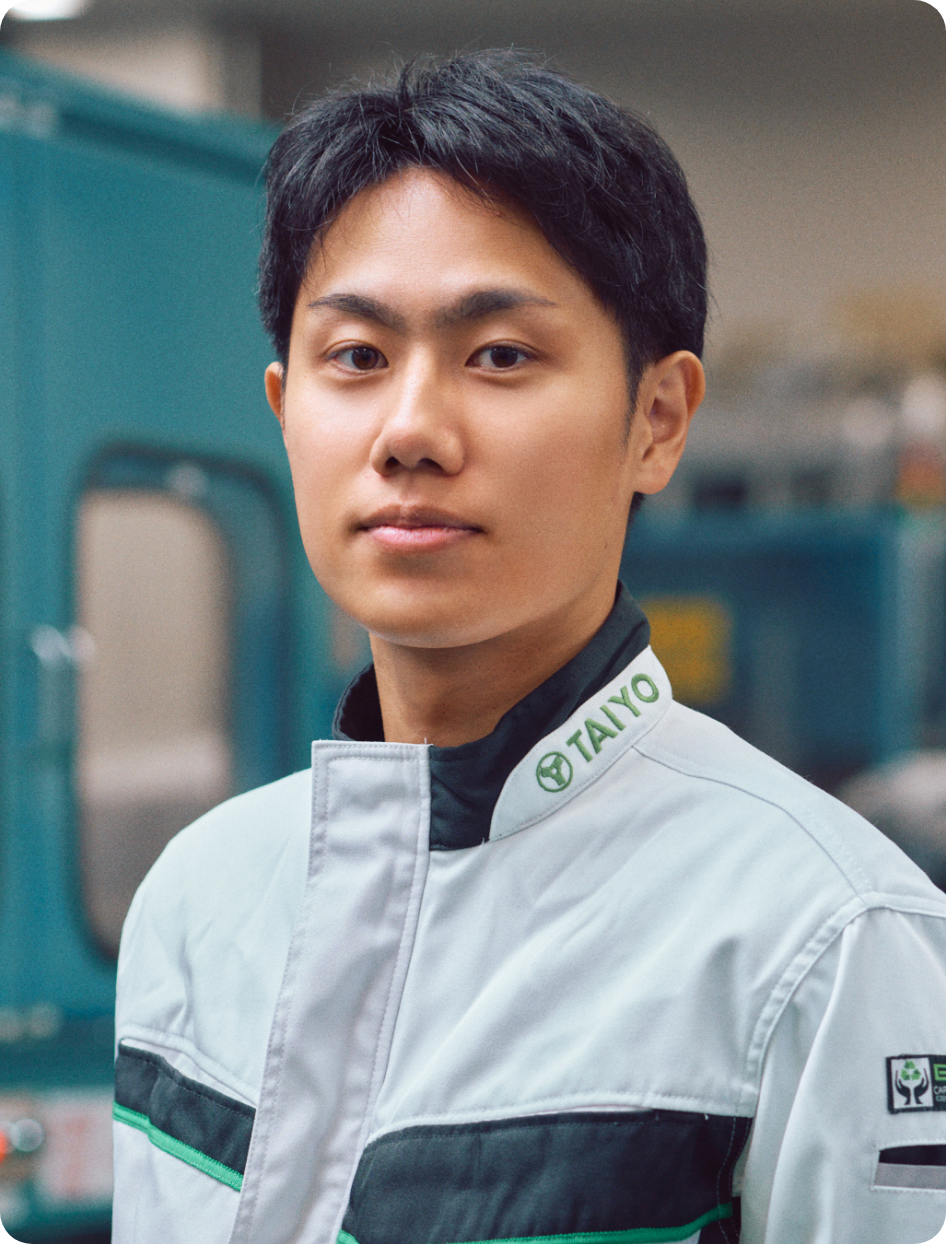
生産技術K.K.北九州事業所 製造技術課
太陽インキ製造株式会社

ITシステムK.Y.情報システム部 企画管理課
太陽ホールディングス株式会社

ビジネスディベロップメントT.Kビジネスディベロップメント部
市場開発課
太陽インキ製造株式会社

医薬品製造販売・製品育成R.O.信頼性保証部 品質保証グループ
太陽ファルマ株式会社

経理M.N.経理部 経理課
太陽ホールディングス株式会社

経理K.H.経理部 経理課
太陽インキ製造株式会社

人事N.K.人事部 採用/人材・組織開発課
太陽ホールディングス株式会社

営業T.K.営業部 海外営業課
太陽インキ製造株式会社

